医学部面接のポイント!回答テクニックや注意点、模擬面接の活用などを解説
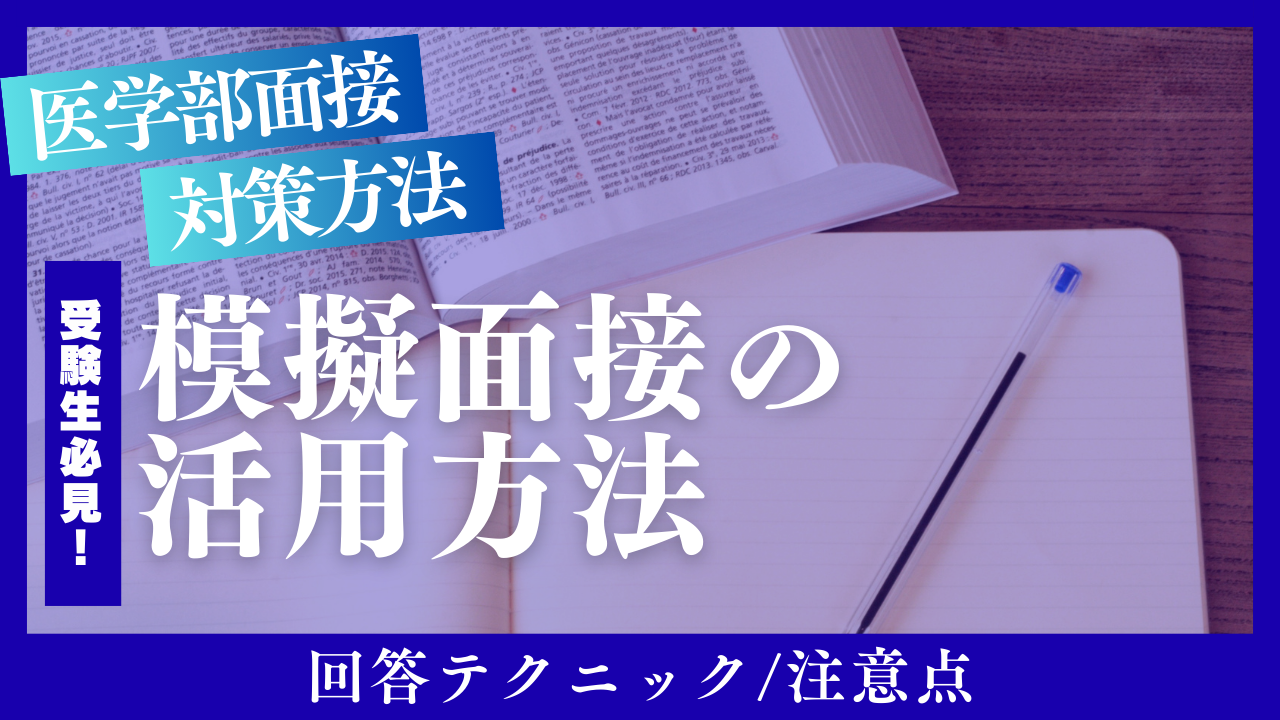
医学部の入試では面接試験が実施されます。
今回は、医学部入試の面接についてまとめました。
記事内では、基本的なポイントやよく聞かれる質問と模範解答の例、また面接時の注意点などについて解説しましたので、医学部の面接対策にご関心のある方はぜひ参考にしてください。
なぜ医学部で面接が重視されるのか
なぜ医学部では面接が重視されるのでしょうか。
その理由は、医師が人々の生命に直接的に関わる職業だからです。
医師は、医学知識や技術を持っていることは前提として、人格面でも優れている必要があります。
面接を通して、コミュニケーション能力や倫理観を測り、医師としての適性があるかを判断します。
また、大学によっては面接を重視しているところもあり、学力試験の成績にあまり差がない場合、面接の評価によって合否が変わることも考えられます。
また、面接で医師としての適性がないと判断された場合は、学力試験での順位に関係なく不合格になる場合があります。
そのため、医学部を志望する方は面接対策もしっかりと行うことが重要です。
医学部面接の基本的なポイント文
まずは、医学部面接の基本的なポイントについてまとめました。
面接の形式
面接試験の形式は、個人面接、グループ面接やグループ討論があります。
また、大学によって面接官の人数や面接回数などが異なります。
一般的にグループ面接は、3〜8人の受験生と3〜5人の面接官で、受験生は面接官から聞かれた質問に順番に答えていく形式です。
グループ討議は、司会者を中心として受験生同士で意見を交わし討論を行います。
テーマは幅広く、医学部入試では医療に関するものが扱われる場合も多いので、日頃からニュースで情報収集をし、自分の意見を言えるようにしておくことが大切です。
個人面接は受験生1人に対して複数人の面接官が質問します。
面接試験に比重が大きい場合、より時間が長く、また回数も多い傾向があります。
評価ポイント
面接試験の内容は大学によって異なりますが、志望動機や自己PR、理想の医師像などはほとんどの大学で尋ねられます。
評価ポイントは内容が適切で明確で具体的な回答であるか、対話能力があるかなどです。
また、医師の仕事を理解しているか、学習意欲があるか、見た目に清潔感があるか、礼儀やマナーがあるかが評価の対象となります。
医師は患者やスタッフと連携をとって適切な対処をしていく必要があります。
コミュニケーション力が不足していると医療ミスを引き起こす恐れがあるため、医学部入試における面接では、会話が成り立つかどうかも試されます。
大学によって、面接試験で重視される部分や出題されるテーマの傾向が大きく異なるため、志望校に合わせた対策を行いましょう。
医学部面接でよく聞かれる質問と模範回答例文
次に、医学部面接でよく聞かれる質問と模範回答の例文についてまとめました。
志望動機と理想の医師像
志望動機と理想の医師像に関する質問は必ずと言っていいほど出題され、医療に対する情熱や医師としての適性を測る上で非常に重要な要素となります。
以下に、様々なケースに合わせた模範回答の例文をいくつかご紹介します。
<志望動機>
ケース1:具体的な経験から医師を志した場合
「中学生の頃、祖母が病気で入院した際、医師の皆さんが献身的に祖母の治療にあたってくださいました。
その姿を見て、私も誰かの役に立ちたいと強く思うようになりました。
特に、祖母の担当であった〇〇先生との出会いが大きく、患者さんの心に寄り添い、温かい言葉をかけてくださる姿に感銘を受けました。
〇〇先生のようになりたいという思いから、医学部への進学を決意しました。」
ケース2:漠然とした思いから医師を志した場合
「幼い頃から、人の役に立つ仕事がしたいと考えていました。
様々な職業がある中で、医師という職業は、人の生命を直接的に救うことができる、最もやりがいのある仕事だと感じています。
特に、〇〇という分野の医療に貢献したいと考えており、〇〇大学医学部でそのための知識と技術を学びたいです。」
ケース3:大学の特徴に惹かれた場合
「〇〇大学医学部は、〇〇という点が特に魅力的だと感じました。
〇〇という研究が盛んであり、私もその分野で貢献したいと考えています。
また、〇〇という教育プログラムも充実しており、将来の医師として必要な能力を養うことができると思い、この大学を選びました。」
<理想の医師像>
ケース1:患者中心の医師
「私は、患者さんの立場に立って考え、寄り添うことができる医師を目指しています。
医学的な知識だけでなく、コミュニケーション能力を大切にし、患者さんと信頼関係を築くことで、より良い医療を提供したいと考えています。」
ケース2:専門性を高めたい医師
「〇〇という分野の医療に特に興味があり、その分野の専門医として、患者さんの治療に貢献したいと考えています。
そのためには、日々新しい知識を学び続け、最新の医療技術を習得することが重要だと考えています。」
ケース3:地域医療に貢献したい医師
「私は、地域医療に貢献し、多くの人々の健康を守りたいと考えています。
特に、〇〇地域のような医療資源が不足している地域で、医師として活躍したいと考えています。」
医療に関する時事問題
医学部面接では、医療に関する時事問題に関する質問が出ることもあります。
これは、医療への関心や社会問題に対する意識を持っているかを測るためのものです。
以下に、模範回答の例文をいくつかご紹介します。
例1:遠隔医療
「最近、遠隔医療という言葉をよく見かけます。
私は、遠隔医療は医療の質の向上と医療格差の解消に貢献できると考えています。
AIを活用した診断補助システムや、遠隔手術の技術の発展により、専門医の不足が深刻な地域でも高度な医療を提供できるようになる可能性があります。
また、慢性疾患を持つ患者さんのための遠隔モニタリングシステムは、患者の生活の質向上にもつながると期待できます。
しかし、遠隔医療の普及には、セキュリティ対策や、患者への適切な情報提供など、解決すべき課題が数多くあります。
特に、個人情報の保護は、遠隔医療において最も重要な課題の一つです。
遠隔医療が将来の医療において不可欠な要素になると考えています。
そのために、医療従事者だけでなく、患者や社会全体で、遠隔医療のメリットとデメリットを理解し、適切なルール作りを進めていくことが重要だと思います。」
例2:AI医療
「AI医療の進展が注目されています。
AIによる診断補助や治療法の提案は、医療の精度向上に大きく貢献すると期待されています。
しかし、一方で、AIの誤診や、プライバシー問題などの課題も指摘されています。
AI医療の導入にあたっては、これらの課題をしっかりと解決し、患者さんの安全を最優先に考えることが重要です。
私は、AI医療のメリットを最大限に活かしつつ、そのリスクを最小限に抑えるような医療システムの構築に貢献したいと考えています。」
自己PR・長所短所
医学部面接では、自己PRや長所・短所について聞かれることが多くあります。
自己PRと長所・短所の例文をご紹介します。
<自己PRの例文>
「私は、高校時代にボランティア活動で病院のお手伝いを経験しました。
そこで、患者さんの笑顔や感謝の言葉を直接聞くことができ、医師という職業の素晴らしさを実感しました。
特に、〇〇という経験を通して、〇〇という能力を養うことができ、将来、医師として患者さんと向き合う上で、この能力が活かせるのではないかと考えています。」
<長所の例文>
例1:責任感
「私は、どんなことにも責任を持って取り組むことを心がけています。
高校時代には、〇〇という経験を通して、責任感の大切さを学びました。」
例2:観察力
「私は、周囲の状況をよく観察することが得意です。
〇〇という経験を通して、観察力を養うことができました。
将来、患者さんの状態を的確に把握することに役立つと考えています。」
<短所の例文(改善策も合わせる)>
例1:完璧主義
「私は、完璧主義なところがあり、少しでもミスがあると、どうしても気になってしまうことがあります。
医療の現場では、完璧な状況はあり得ません。
そのため、完璧を求めすぎず、柔軟に対応できるよう日々努力しています。」
例2:緊張しやすい
「私は、人前で話すときや、初めてのことに挑戦するときに緊張しやすいという一面があります。
しかし、バイトの接客やボランティア活動を通して、少しずつ克服できるように努めています。」
学生時代の経験
学生時代の経験を通じて培ったスキルや価値観を述べることが重要です。
コミュニケーション能力やチームワーク、問題解決力は特に医師に必要なため求められます。
「部活動でのリーダー経験を通じて、チームワークや責任感を学びました。
困難な状況でも冷静に対応し、仲間と協力して目標達成に導いた経験は、医師としても役立つと考えています。」
地域医療の現状
医療に対する関心や考えを知るために、地域医療の現状について質問されることはよくあります。
以下は模範解答の一例です。
この解答を参考にしつつ、自分の考えを加えていくと良いでしょう。
「地域医療の現状は、都市部と地方部で大きな格差が存在しています。
特に地方では医師の偏在が深刻であり、都市部の病院や診療所には医師が集中している一方で、地方や過疎地では医師不足が続いています。
このため、住民が必要な医療を受けることが難しくなり、病院や診療所の数が減少している地域もあります。
これらの課題に対処するために、政府は地域医療の支援策を講じています。
しかし、医師の過重労働や、地域に根ざした医療の担い手不足といった課題は依然として残っています。
そのため、私が医師となることで、地域医療に貢献したいと考えています。
特に、医師としての役割だけでなく、地域の医療スタッフや住民と連携し、予防医療や健康教育にも力を入れていきたいと思います。」
中学・高校時代の経験(部活動やボランティアなど)
中学校や高校で取り組んだことに対しては、部活動やボランティアなどの課外活動を答えるのが一般的です。
その課外活動で何を得て医師としてはどう活かすかを伝えられるようにしておきましょう。
模範解答をご紹介します。
「私は○○時代に○○部に所属していました。
最初は~~することが苦手でしたが、朝練や自主練を積み重ね、上達し、県大会出場を達成しました。
○○部で頑張ったことで努力することは必ず自分に繋がるという事とチームワークの大切さを学びました。
この学んだことを活かして医師として活躍したいと考えています」
質問に解答する際に注意すること
質問に解答する時には、誠実さと冷静さを持って対応することが重要です。
面接官はストレス耐性を知るためにあえてセンシティブな部分に触れることもありますが、感情のコントロールは自分でできるようにし、知的さをアピールしておきましょう。
また、知ったかぶりはしないようにしましょう。
面接官はいままで多くの受験生の面接を行っており、知識や情報も豊富であるため、取り繕ったものは見抜かれてしまいます。
分からない場合は正直に認め、さらに学びたいという姿勢を示すことで面接官に好印象を与えられます。
面接官に好印象を与える回答テクニック文
続いて面接官に好印象を与える回答テクニック文についてご紹介します。
STAR法を活用した具体的な回答方法
STAR法を用いることで面接官が聞きたい事をしっかりと伝えることができます。
situation(状況),task(課題),action(行動),result(結果)に沿って答えていきましょう。
situation(状況):具体的な状況を説明し、実際に経験したことを挙げます。
task(課題):その状況下において何が課題であったのかを説明しましょう。
action(行動):その課題を知ってどう行動したのかを伝えましょう。
result(結果):その行動がどのような結果をもたらしたのかを伝えます。
このSTAR法を用いることで自分自身も話題に集中でき、本質からずれた回答になることを避けてくれます。
医学的視点と人間性のバランス
また、医学的視点と人間性のバランスを用いることも有効的です。
解答例をご紹介します。
「私はボランティア活動を通じて、患者さんとの信頼関係の大切さを学びました。
医学的な知識や技術も重要ですが、患者さん一人ひとりの背景や気持ちを理解し、寄り添うことが医療において不可欠だと感じています。
医師として、科学的な根拠に基づいた治療を行うと同時に、患者さんの人間性にも配慮し、心身ともに支える医療を提供したいと考えています。」
医学的視点になりすぎると機械的に感じ取られてしまうため、人間性を程よくいれることで医師という患者さんとの対話も非常に重要な職業に適していると思わせることができます。
NGワードとその言い換え方
これまで面接官に好印象を与えるテクニックについてご紹介しました。
面接において減点を出来るだけ減らすために続いては、NGワードとその言い換え方についてご紹介します。
医者
医者という言葉は、敬意や専門性がないと捉えられてしまう可能性があります。
医者は医療人の方全員に当てはまるためです。
そのため、「医師」という言葉を使うようにしましょう。
看護婦
看護婦は女性のみを表します。現代のジェンダー観に合わせて看護師を用いるようにしましょう。
わかりません
「わかりません」と伝えてしまうと積極性・意欲に欠けていると捉えられる場合があります。
そのため、「1分ほど考えさせていただいてもよろしいでしょうか」「現在の知識では正確に答えられないため、後程調べさせていただきます」などと伝えるようにしましょう。
親に言われたので
「親に言われたので」と伝えると自分の意志ではないと捉えられます。
医学部に入学すれば厳しい学業や実習があるため、そのような他人まかせに聞こえる言葉は使わず、きっかけは親であったとしてもそこから自分がどう思い、行動したのかを伝えるようにしましょう。
面接時の注意点
続いて面接時の注意点についてご紹介します。
適切な姿勢と表情にする
まずは適切な姿勢と表情にしましょう。
姿勢は着席の際には背筋を伸ばし姿勢を正して椅子に浅く座ります。
背もたれに深く腰を掛けず、猫背にも注意しましょう。
表情は自然で柔らかい表情を心がけることで、相手に好印象をもたらすことができます。
口角を上げる程度が適切です。
声のトーンと話すスピードに気を付ける
声のトーンや話すスピードにも気を付けましょう。
声のトーンはワントーン上げることで、明るい印象をもたらすことができます。
スピードについては、緊張するとどうしてもはやくなってしまうため、落ち着いて話すようにしましょう。
目安として1分間に300文字程度話せるくらいで練習しておきましょう。
面接室での立ち振る舞いにも注意する
面接室での立ち振る舞いとしては、入室から退出まで心がける必要があります。
基本的に姿勢を正して丁寧な挨拶を心がけましょう。
ノックはゆっくりと3回、ドアを開けたら椅子の横に立ちましょう。
面接官の合図があってからお辞儀と「失礼します」と言って着席をしましょう。
退出時は椅子の横に立ってから入室時と同じく姿勢を正してお辞儀をします。
ドアの手前まで来たら、もう一度面接官の方を向いて「失礼します」と言ってお辞儀をして、静かに退出しましょう。
模擬面接の効果的な練習方法
続いて模擬面接の効果的な練習方法についてご紹介します。
録画で自己分析する
まずは一人でできる方法として、面接を録画して自己分析を行いましょう。
録画することで客観的に改善点や弱点に気づくことができます。
言葉遣い、話し方、表情、声のトーン・スピード、間の取り方が適切であるか注意しましょう。
カメラを面接官だと思い、できれば本番と同じ服装で行うことで、本番も焦らずに面接を受けることができます。
第三者からのフィードバックを受ける
第三者からのフィードバックをもらうことも効果的な面接の練習方法です。
面接官役は家族や友人でも大丈夫です。
まずは、だれかに見てもらいながら話すことに慣れましょう。
続いて可能であれば、面接対策を行っている予備校の先生などに面接官目線のフィードバックをもらいましょう。
そして貰った意見を改善できるように、練習を積み重ねましょう。
再受験者・社会人向けの面接のポイント
続いて再受験者・社会人向けの面接のポイントについてご紹介します。
経験を活かした志望動機にする
再受験生や社会人ならではの強みとして、社会人として得た経験や他学部卒業だからこその視点があります。
これらの経験をアピールすることで、現役生にはない強みを示すことができます。
また、再受験生や社会人として、すでに培った社会経験や人間関係構築力を医師としてどう活用したいかを強調しましょう。
特に、医師に必要な思いやりや責任感を持ち合わせていることを示すと良いです。
年齢に関する質問へ適切に対応する
再受験生や社会人の方が年齢に関する質問を受けた場合、その質問に対して前向きで自信を持った態度で回答することが重要です。
年齢を理由にネガティブに捉えるのではなく、経験や人生の視点を活かす姿勢を強調しましょう。
年齢を重ねることで、若い時とは異なる視点や価値観を得たことを強調します。
また、社会経験を通じて得た問題解決能力や人間関係の構築力など、医師として役立つスキルをアピールしましょう。
年齢に関係なく、医師としての強い意志や情熱を持っていることを伝えられると良いでしょう。
まとめ
今回は医学部の面接についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
医師になるためには患者さんや看護師さんなど多くの人とのコミュニケーションは欠かせません。
そのため、面接ではやってきたこと・やりたいことはもちろん、人柄なども見られています。
また、学科試験の対策ばかりになりがちですが、面接も医学部に入学するためには非常に重要ですので、早期から対策にとりかかるようにしましょう。