国公立大学医学部に合格するのはやばいくらい難しい?難易度が高い理由や倍率について解説
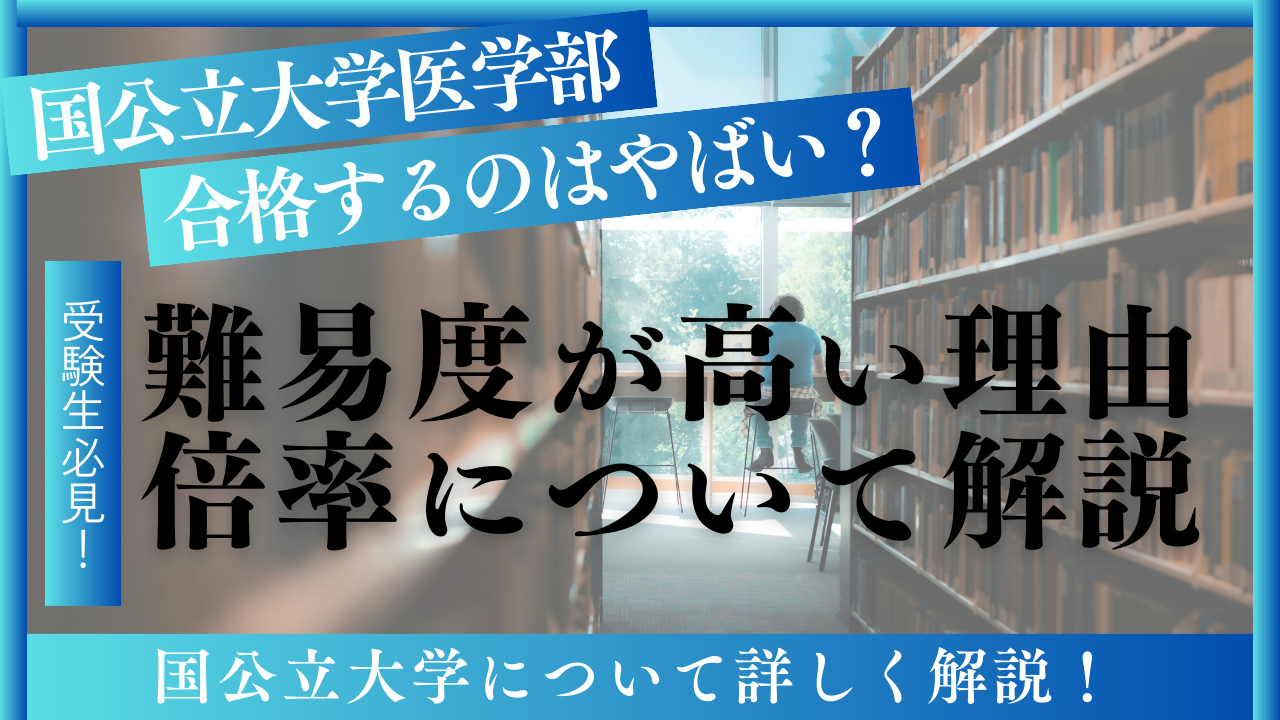
国公立大学医学部と聞くと、難易度が高い」「とイメージされる方も多いのではないでしょうか。国公立大学の医学部は日本の中でも最難関の受験と言われており、僅か2%の受験生しか合格できないと言われています。
この記事では国公立大学の医学部に入るのがどれくらいやばいのか、難易度がどれほど高いのかについて詳しく解説しています。国公立大学医学部に入学したい方は是非参考にしてください。
国公立大学医学部受験は日本の最難関!どれくらいすごい?
国公立大学医学部受験は非常に難易度が高く、日本の最難関だといわれています。実際にどれくらいの難易度なのかを以下で詳しく解説していきます。
全受験生の2%しか合格できない
国公立大学医学部を受験して合格する難しさを例えると、全受験生の2%しか合格できないほどのレベルです。これは、受験生が1万人だとしたら、そのうち合格するのは200人程度という計算になります。この割合は国公立大学医学部の受験の難しさと、競争の激しさを示す重要な指標となります。
国公立大学医学部の入試の難易度は別格
国公立大学医学部の入試は、数多くある大学の中でも特に厳しい競争となり、そして高い学力が求められます。偏差値のレベルも非常に高く60後半から70前半と高い水準であり、共通テストでも高い得点率が必要です。そのため、国公立大学医学部の入試の難易度は、東京大学や京都大学といった最難関大学と同じくらい別格だといえます。
国公立大学医学部が最難関とされている理由
続いて、国公立大学医学部が最難関とされている理由について詳しく解説していきます。
1:競争率・倍率が高いから
まず1つ目の理由として、競争率・倍率が高いことがあげられます。医学部は他の学部よりも人気が高く、毎年多くの受験生が集まっています。しかし、定員が他の学部と比べると非常に少なく、特に国公立大学医学部は入学定員が限られており、東京大学や京都大学、大阪大学などのトップ校だと競争率はさらに高くなります。そのため、受験生の中で合格を勝ち取るのは極めて難しく、わずかな人数しか合格できない状況となるため最難関とされています。
2:筆記試験以外の対策も必要になるから
2つ目の理由として、筆記試験以外の対策も必要になることがあげられます。医師は社会的責任が非常に大きい職業です。そのため、医学部受験では筆記試験に加えて、医師としての素質や人間性、責任感も問うために面接や小論文が課され、医師としての適性が試されます。ただでさえ医学部受験では高い学力が求められ、相当の学習量が必要となるうえに、面接や小論文の対策もしておく必要もあることから、国公立大学医学部が最難関とされている理由の一つとなっています。
3:入試科目が多く二次試験の難易度がかなり高いから
3つ目の理由として、入試科目が多く二次試験の難易度がかなり高いことがあげられます。国公立大学は私立大学と違い、共通テストの受験が必須となります。そのため、共通テスト5〜7科目と個別試験4科目を受験する必要があり、私立大学よりも入試科目が多くなっています。また、二次試験では高難易度な問題が出題される傾向にあり、英語では単語数が多かったり、理科ではややマニアックな問題が出題されるなどレベルが高くなっています。これらの要因も、国公立大学医学部が最難関とされている理由だといえます。
4:大学ごとに問題の癖が異なり解きづらいから
4つ目の理由として、問題の癖が異なり解きづらいということがあげられます。医学部入試の問題は大学によって傾向が大きく異なる場合があります。志望大学の問題傾向に慣れるために、膨大な学習を行う必要がある点も国立大学の医学部入試が難しいといわれる理由の一つでしょう。人によって入試問題の相性は異なるため、偏差値を抜きにして、赤本で過去問を解いてみて自分が勝負できそうな医学部を探すことが重要です。
国公立大学医学部の入試情報
次に国公立大学医学部の入試情報について解説します。
倍率はどれくらい?
国公立大学は学部によって学費が変わらず一律であり、私立大学医学部と比較して非常に安く進学できるため、倍率は高い傾向があります。2024年度の前期国公立大学医学部医学科入試の志願倍率は、最も高い大学が愛媛大学で10.3倍でした。最も低い大学は徳島大学で2.4倍でした。後期の志願倍率は、最も高い大学が旭川医科大学で66.8倍、最も低い大学が福井大学で12.1倍でした。前期入試の倍率は私立大学医学部よりも低い場合がありますが、国公立大学は前期後期で1校ずつしか受験できないため、やや見方が異なります。また、2024年度で最も倍率が低かった徳島大学は二次試験が英語と数学の2科目しかないため、失敗を恐れる受験生が避けていると考えられます。低倍率でも難易度が易しいわけではないため、注意が必要です。
共通テストのボーダーはどれくらい?
国公立大学の受験では、個別試験のほかに共通テストの結果も合否に関係します。2023年度の実施結果から算出した2024年度共通テストのボーダーは、最も高い東京大学で92%、最も低い旭川医科大学、弘前大学、福島県立医科大学、群馬大学、富山大学、島根大学、山口大学、愛媛大学、高知大学、大分大学、琉球大学で80%でした。国公立大学医学部医学科受験では最低でも共通テストで80%の得点が必要です。また、志願者数が多い場合は二段階選抜が実施され、実際のボーダーが高くなることがあるので、受験情報もしっかりとチェックしておきましょう。
2次試験の難易度は?
大学によって二次試験は問題の癖が強く、かなり難易度は高いといえます。また、共通テストよりも二次試験の比率が高く設定されている大学もあります。二次試験の難易度が極端に難しい大学では共通テストで点数が取れても二次試験で不合格となってしまう場合があります。また、小論文や面接試験では、学科試験の成績が合格基準を満たしていても医師としての適性がないと判断された場合は不合格となるため、手を抜かずにしっかりと対策をする必要があるでしょう。
国公立大学医学部でも入学しやすい大学はある?
基本的に、国公立大学医学部の入試レベルは最難関といえます。ここでは、その中でも比較的偏差値が低めの大学をご紹介します。
札幌医科大学
まずご紹介するのは、札幌医科大学です。札幌医科大学医学部は、地域医療の発展に貢献することを目指しており、特に北海道内で活躍する医師の育成に力を入れています。
札幌医科大学の二次試験の問題は標準レベルであり、面接も癖がない内容のため、比較的入試レベルが易しい大学となっています。二次比率は、750:800で配点合計は1550点です。共通テストのボーダーラインは82%で、二次試験の目標得点率は60〜80%です。二次試験の問題は標準的なものが多いですが、試験時間が短いため、時間配分を意識した対策が必要となるでしょう。
秋田大学
秋田大学医学部は、地域医療と先進医療の両立を目指した教育と研究で高い評価を得ています。特に、地域医療の担い手を育成する「地域枠入試」や、地域に密着したカリキュラムが特徴です。
秋田大学医学部の二次試験は数学と英語の2科目であり、数学の難易度はやや高く、英語の難易度はやや低めとなっています。二次比率は、600:400で配点合計は1000点です。共通テストのボーダーラインは83%で、二次試験の目標得点率は数学は60〜80%、英語は80%~です。
秋田大学医学部は共通テストを重視した配点となっているため、共通テストでしっかり点数を取れるよう対策することと、また、他の国公立医学部と比べて秋田大学医学部は面接の配点が200点と高いため、面接対策もしっかりと行う必要があります。
山形大学
山形大学医学部は、地域医療への貢献と先進医療の融合を目指す教育が特徴です。「地域枠入試」を通じて、地元で活躍する医師を育成しており、地域密着型の医療実習や研修が充実しています。
山形大学医学部の二次試験は標準レベルの問題が多いですが、数学は医学部固有問題がやや難しくなっています。二次比率は、950:700で配点合計は1650点です。共通テストのボーダーラインは84%で、二次試験の目標得点率は数学と理科は60〜80%、英語は80%~です。
山形大学医学部は共通テストの配点の比重が大きいですが、二次試験も他の国公立医学部と比べると高得点をとる必要があるといえます。苦手科目があると不利になりやすいため、過去問演習を通して入念に対策しておきましょう。
福島県立医科大学
福島県立医科大学医学部は、震災後の復興医療や放射線医学研究で国内外から注目を集めています。地域医療の担い手を育成する「地域枠入試」を設け、県内の医療格差解消に貢献しています。また、放射線医学の研究拠点として、先端的な技術や知見を活用した教育と研究が特徴です。
福島県立医科大学医学部の二次試験は数学と英語が難問中心の出題となっています。二次比率は、700:660で配点合計は1360点です。共通テストのボーダーラインは83%で、二次試験の目標得点率は数学と理科は60〜80%、英語は~60%です。
福島県立医科大学医学部は共通テストと二次試験の配点比率がほぼ同じであるため、どちらもきちんと点数をとることを目指しましょう。また、二次試験では特に数学の出題レベルが高いといわれているため、重点的に対策を行いましょう。
鳥取大学
鳥取大学医学部は、地域医療への貢献と先端医療技術の融合を重視しています。特に、鳥取県内の医療機関との連携による実践的な臨床教育が充実しており、地域医療の担い手を育成しています。また、がんや遺伝性疾患の研究に力を入れ、先端医療の発展に寄与しています。
鳥取大学医学部の二次試験は全体的に標準問題中心の出題となっています。二次比率は、920:700で配点合計は1620点です。共通テストのボーダーラインは82%で、二次試験の目標得点率は数学と英語は60〜80%、理科は80%~です。
鳥取大学医学部は共通テストの比率が高いため、共通テストの対策を入念に行う必要があります。また、二次試験では基礎を重視している傾向にあるため、標準レベルの問題を正確に解けるようにしておきましょう。
香川大学
香川大学医学部は、地域医療の担い手育成を重視した教育が特徴です。四国地域の医療機関と連携し、臨床実習では実践的なスキルを習得できます。特に、地域医療と予防医学に力を入れており、香川県の医療課題解決に向けた研究も活発に行っています。少人数制教育により、学生一人ひとりに丁寧な指導が行われ、医師としての実力と倫理観を磨くことができます。温暖な気候と豊かな自然に囲まれた環境で、地域密着型の医療を学びたい学生に最適な環境です。
香川大学医学部の二次試験は全体的に標準問題中心の出題となっています。二次比率は、700:700で配点合計は1400点です。共通テストのボーダーラインは83%で、二次試験の目標得点率は数学は60〜80%、英語と理科は80%~です。
香川大学医学部は共通テストと二次試験の配点に偏りがありません。二次試験の難易度は比較的易しいといわれているため、いずれの科目でも十分に点数をとれるよう学習しておきましょう。また、面接の配点は100点とやや低めですが、面接対策も欠かさず行いましょう。
和歌山県立医科大学
和歌山県立医科大学は、地域医療の担い手を育てる教育と最先端の研究が融合した大学です。特に、救急医療や高齢化社会に対応した地域医療の実践教育が充実しています。和歌山県内の医療機関と強力に連携し、学生は幅広い臨床実習の機会を得られます。また、循環器や再生医療の研究分野で高い評価を得ており、医療の発展に貢献しています。少人数制で丁寧な教育が受けられる環境の中、地域医療を支える使命感と実践力を身につけられる大学です。
和歌山県立医科大学医学部の二次試験は、標準問題からやや難易度が高いものまで出題されています。二次比率は、600:700で配点合計は1300点です。共通テストのボーダーラインは82%で、二次試験の目標得点率は数学と理科は〜60%、英語は60~80%です。
和歌山県立医科大学医学部は二次試験を重視した配点となっています。そのため、共通テストで思うように点数が伸びなかったとしても挽回できる可能性があります。二次試験を意識した学習に取り組み、特に数学と理科の配点は各250点と英語と比べるとやや高いため、数学と理科を得点源にできると有利になるといえるでしょう。
琉球大学
琉球大学医学部は、沖縄を拠点に地域医療と国際医療の両方に対応する教育が特徴です。離島医療を含む地域密着型の実習が充実しており、多文化共生社会での医療人育成を目指しています。また、熱帯医学や感染症に関する研究が盛んで、国内外から注目を集めています。学生は少人数制の環境で、医療の基礎から臨床まで丁寧に学ぶことができ、地域医療に貢献したい人や国際的な視野を持つ医師を目指す人に最適な学びの場です。
琉球大学医学部の二次試験は全体的に標準レベルの問題が出題されています。二次比率は、1000:800で配点合計は1800点です。共通テストのボーダーラインは83%で、二次試験の目標得点率は数学は80%~、英語と理科は60~80%です。
琉球大学医学部は共通テストを重視した配点となっています。そのため、共通テストで点数をとれなかった場合、二次試験で取り返すことは難しいといえます。入念に共通テスト対策を行い、また、他の大学と比べると面接の配点が200点と高いため、面接対策にも力を入れる必要があります。
国公立大学医学部は独学で目指せる?
次に国公立大学医学部は独学で目指せるのかについてまとめてみました。
医学部は独学で目指すのは難しい
国公立医学部を独学で目指すのは難しいとされています。その理由は、まず試験範囲が広く、基礎から応用まで深い理解が求められることです。医学部の入試では、理系科目だけでなく、英語や国語も高得点が必要です。独学では、効率的な学習計画を立てることや、自分の弱点を正確に把握するのが難しく、学習が非効率になる可能性があります。さらに、模試や過去問の分析、傾向対策など専門的な知識も必要です。予備校や塾では、これらを体系的に学び、専門講師からの指導を受けられるため、独学よりも合格への近道となることが多いです。独学の場合、情報収集力や自己管理能力、精神的な強さが不可欠であり、それが難しさにつながるのです。
医学部予備校への入学をおすすめ
医学部を目指す受験生には、医学部専門の予備校への入学をおすすめします。理由の一つは、医学部入試に特化したカリキュラムが整っている点です。難関大学特有の試験傾向や科目ごとの攻略法を学ぶことで、効率的に学習を進められます。また、予備校では少人数制の授業や個別指導が行われることが多く、自分の弱点や理解度に合わせたサポートを受けられるのが魅力です。さらに、同じ目標を持っている仲間と切磋琢磨できる環境は、受験期のモチベーションの維持向上にもつながるでしょう。特に医学部受験は試験範囲が広く、難易度も高いため、自己流では対応が難しいことが多いです。専門予備校に通うことで、合格への最短ルートを確保できる可能性が高まります。
国公立大学医学部受験に合格するなら医進の会
国公立医学部受験を目指すなら、「医進の会」の利用をおすすめします。「医進の会」は、医学部受験に特化したプロフェッショナルな学習支援を提供する予備校で、難関校合格に必要なすべてのサポートを受けられる環境が整っています。特に個別指導に力を入れており、生徒一人ひとりの学習進度や弱点に合わせたオーダーメイドのカリキュラムが特徴的となっています。これにより、効率よく学力を伸ばし、苦手分野を克服することができます。また、医進の会では、医学部入試に精通した専門講師陣が指導を行い、過去問分析や試験傾向に基づいた対策を徹底しています。加えて、少人数制の授業や充実した質問対応体制により、細やかな学習フォローが可能です。さらに、模試や面接対策、小論文指導も充実しており、総合的に入試準備を進められるのも魅力です。医学部合格には学力だけでなく、正確な情報や戦略的な学習が不可欠です。「医進の会」は、そのすべてを兼ね備えた学びの場であり、目標達成の心強いパートナーとなるでしょう。
医進の会についてもっと詳しく知りたい方はこちら
まとめ
国公立大学医学部は、難関でありながら高い人気を誇ります。その魅力は、学費が私立大学と比べて低額であることや、全国に設置されているため地域医療に貢献できる点にあります。入試では理系科目に加え、英語や国語など幅広い学力が求められ、高い競争率を誇ります。地域枠や推薦入試を設けている大学も多く、地域医療に貢献する人材育成に力を入れています。合格には戦略的な学習が不可欠であり、専門予備校や計画的な学習を活用することが成功への鍵となります。