私立医学部の学費が払えない!知っておくべき7つの対策法や払えない場合に起こること
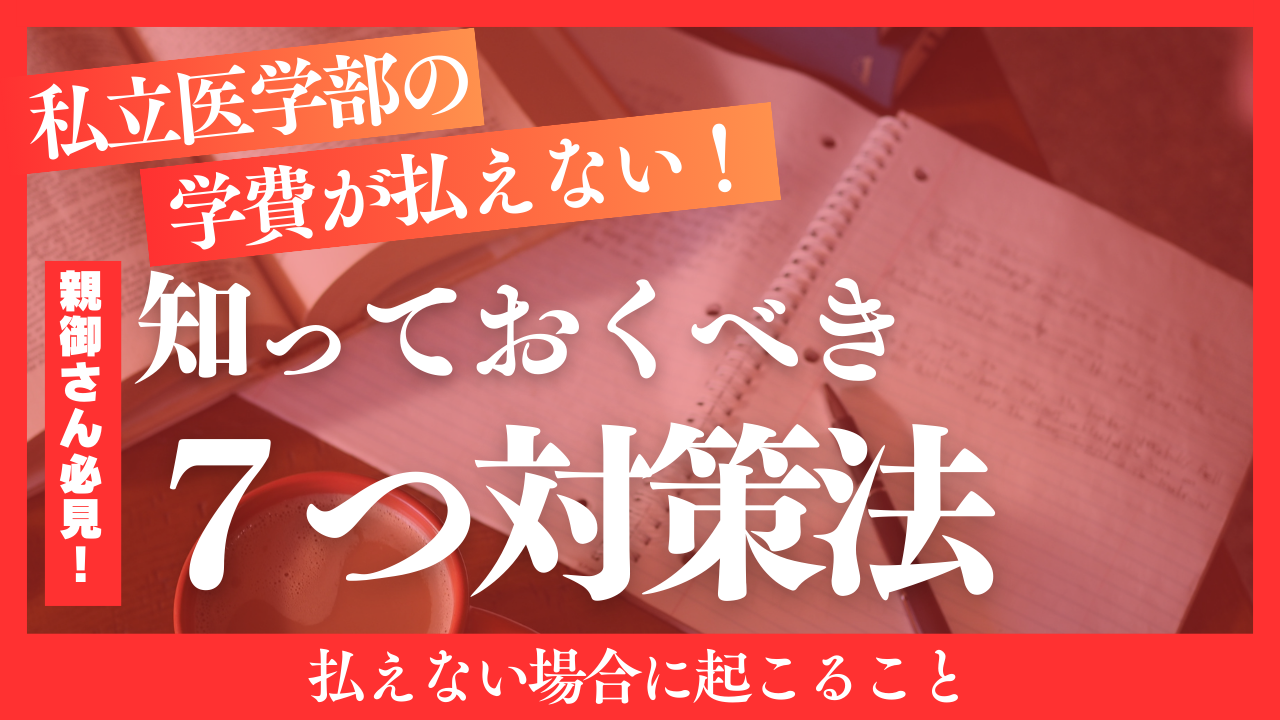
私立医学部を目指しているが、高額な学費が理由で困っている方も多いでしょう。
そこで今回は、私立医学部の学費が払えないときの7つの対策を解説します。
記事内では、医学部の学費の実態や学費が払えないときに起こることなども紹介していますので、私立医学部の学費について知りたい場合はぜひ参考にしてください。
私立医学部の学費の実態
まずは、私立医学部の学費の実態について詳しく解説していきます。
平均的な学費の総額
私立医学部の平均的な学費の総額は、約2,000万円だといわれています。
学費の内訳は、入学金50~100万円、年間授業料100〜200万円、施設費や実習費が年間30~100万円、その他教材費等が年間10~30万円であり、これらの費用が6年かかるため総額として約2,000万円ほどになります。
国公立医学部の6年間の学費総額は約350万〜500万円といわれているため、国公立医学部と比べると非常に高額であることがわかります。
学費が最も高い大学と最も低い大学の比較
現在、私立医学部で学費が最も高い大学は川崎医科大学であり、学費の総額は約4,700万円ほどになります。
反対に、私立医学部で学費が最も低い大学は国際医療福祉大学であり、学費の総額は約1,850万円ほどになります。
このように、同じ私立医学部であっても学費には約2,500万円以上の差があり、大学ごとに負担が大きく異なります。
学費が払えない場合に起こること
私立医学部の学費は高い傾向にあることが分かりましたが、もし学費が払えない状況になってしまった場合どのようなことが起こるのでしょうか。
私立医学部では、学費未納による退学処分となる可能性があります。
大学ごとに学費納入の期日が設けられており、未納の場合、期日を過ぎると大学から通知が送られることが一般的です。
そして、学費未納が続く場合は大学から再度の通知や督促が行われ、未納が解決しない場合、最終的には退学となるケースがあります。
学費が払えない状況を一時的に回避し、経済的な準備を整えるための時間を得る方法として、休学という選択肢もあります。
休学は、学費未納で退学を避けるための有効な選択肢ですが、期間中の計画と復学後の見通しをしっかり立てることが重要です。
また、休学にはメリットとデメリットがあり、休学中に十分な資金を準備できない場合、復学が難しくなることもあるため注意が必要です。
学費支払いに困ったときの7つの対策
学費が払えない場合でも、いくつか対策方法があります。
ここでは、7つの対策をご紹介します。
1. 奨学金制度の徹底活用
まず、1つ目は奨学金制度の徹底活用です。
奨学金制度は多くの大学で利用することができます。
奨学金には、「日本学生支援機構の奨学金」や「大学独自の奨学金制度」などがあり、これらの奨学金制度を上手に活用することで、経済的な負担を軽減し、学業に集中することが可能となります。
以下で、「日本学生支援機構の奨学金」と「大学独自の奨学金制度」について詳しく解説します。
日本学生支援機構の奨学金
日本学生支援機構は、日本国内の学生を対象に、貸与型と給付型の奨学金を提供しています。
貸与型奨学金は、さらに第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)に分かれています。
第一種奨学金(無利子)は成績優秀者で、かつ家庭の収入が一定基準以下の学生、第二種奨学金(有利子)は第一種よりも広範囲の学生が対象であり、収入や成績基準が緩やかとなっています。
給付型奨学金は家庭の収入や学力基準を満たせば、返済不要の奨学金を受けられます。
大学独自の奨学金制度
大学独自の奨学金制度は、私立大学をはじめ、多くの大学が設けています。
これらの制度は、主に学業優秀者や経済的に困難な学生を支援する目的で提供されており、各大学によって内容や条件が異なります。
そのため、各大学の公式ホームページや入学案内で詳細な情報を確認しておきましょう。
また、奨学金には申し込み期限や特定の条件がある場合が多いため、早めに情報収集して申し込み準備を整えることをおすすめします。
2. 教育ローンの賢い利用法
2つ目は、教育ローンを賢く利用しましょう。
入学後に学費の支払いが困難になってしまった場合は、教育ローンを利用することも一つの方法です。
教育ローンにもいくつかの種類があります。
以下では、「国の教育ローン」と「民間金融機関の教育ローン」について詳しく解説します。
国の教育ローン
国の教育ローンは日本政策金融公庫が提供しており、学費を支払うための融資として広く利用されています。
特に、国公立・私立の大学、専門学校、短期大学、大学院など、幅広い教育機関の学費に対応しています。
貸付額は最大350万円(年単位)、利率は2023年時点では年1.78%となっています。
返済期間は最長15年で、返済方法は月々の定額返済といった特徴があります。
低金利であるため、通常の銀行ローンよりも負担が少ないことや、返済開始が卒業後6ヶ月後からで、返済期間も長いため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。
民間金融機関の教育ローン
民間金融機関の教育ローンは、学費をはじめとした教育関連の費用をカバーするために提供される融資です。
銀行、消費者金融、信販会社などが取り扱っており、それぞれに特徴があります。
銀行が提供する教育ローンは、比較的低金利で長期の返済が可能ですが、審査が厳しく、金利が銀行ごとに異なる場合があります。
通常、学費や生活費に利用できるローンとして広く利用されています。
消費者金融が提供する教育ローンは、融資スピードが速く、審査が柔軟であるため、急な資金需要に対応できる点が特徴です。
しかし、金利は銀行ローンに比べて高めで、借入額や返済期間にも制限があります。
信販会社が提供する教育ローンは、学費を支払うために利用されることが多く、銀行ローンより金利が少し高いものの、融資条件が比較的緩く、審査が通りやすい点が魅力です。
民間金融機関の教育ローンは、選択肢が豊富であり、金利や返済条件、融資額などが異なります。
自分のニーズに合わせて最適なローンを選び、慎重に返済計画を立てることが重要です。
3. 学費免除・減額制度の探索
3つ目は、学費免除や減額制度の利用です。
大学によっては、特定の条件を満たせば学費免除を受けられる場合もあります。
また様々な支援制度も設けられております。
各大学によって異なりますが、主な制度についてご紹介します。
成績優秀者向け特待生制度
成績優秀者向け特待生制度は、成績優秀な学生を対象として、学費の減免や免除等の優遇措置を行う制度です。
日本医科大学、慶應義塾大学、大阪医科薬科大学、関西医科大学等で特待生制度を設けています。
特待生制度の対象となるのは、入試や在学中の成績、スポーツや文化活動などの成績が優秀な学生であり、経済状況等は考慮されません。
特待制度の例として、「1年次の授業料を免除」「年間授業料を給付」「施設拡充費や教育充実費を免除」といったものがあります。
経済的困窮者向け減免制度
国公立大学の多くは、経済的な事情により学費の支払いが困難である学生に対して様々な対策を取っています。
そのほとんどは、直近で起こった台風や地震等の災害の被災者を対象としています。
また、2020年4月以降、文部科学省による高等教育無償化制度が始まりました。
高等教育無償化制度とは、経済的事情で進路を諦めることの無いように、低所得者世帯を対象に設けられた制度です。
住民税が非課税である世帯と、それに準ずる世帯が対象となります。
免除額には上限がありますが、国公立大学は私立大学よりも学費は安価であるため実質的に「学費ゼロ」で進学することもできます。
2025年度からは多子世帯(子供3人以上)は、所得制限なく大学の授業料・入学金が無償化され、医学部も対象となっておりますので、検討してみてはいかがでしょうか。
4. アルバイトと学業の両立
4つ目は、アルバイトと学業を両立させることです。
実際にアルバイトをしている医学生は50%弱で、全学部におけるアルバイトしている学生は60〜70%程ですのでやや割合は少ないとは言え、アルバイトと医学部の学業とを両立している学生は多くいます。
ただし、学年が上がると学業が忙しくなり、アルバイトにかける時間は少なくなるようです。
最優先は学業ですので、他の学部に比べても学習内容が豊富であり、学業に時間が多く取られてしまう医学部生が、アルバイトだけで学費を支払うのはとても難しいといえます。
5. 休学制度の活用と計画的な復学
5つ目は、休学制度の活用と計画的な復学です。
医学部の授業料はとても高額で、授業の空き時間でバイトをして支払うのは厳しいといえます。
そのため、学費が用意できない状況になった場合は、休学してフルタイムで働きお金を貯めるという選択肢もあります。
休学中は基本的に授業料の支払いはなく一部諸経費に限られるので、フルタイムで働けば、ある程度のお金は用意することができます。
しかし、医学部の学費は年間数百万にも上るため、フルタイムで働いても授業料の支払に十分な金額を稼ぐことができない場合があります。
もう一度休学してお金を貯めなくてはならないということにもなりかねないため、休学をする際は計画的に行う必要があるでしょう。
6. 転学
6つ目は、転学です。
今いる大学よりも授業料が安い他大学に転学するというのも一つの方法です。
医学部から他大学の医学部への編入は認められていない場合が多いため、基本的には一度理系学部に編入後、医学部学士編入を受験することになります。
国公立大学への転学
国公立大学は学費が学部に関わらず基本的に一律であるため、医学部には6年間で約350万円程度で行くことができます。
一旦国公立大学の理系学部に編入し、その後医学部編入試験の受験資格を得るか、もしくは一般受験となります。
国公立大学医学部は受験において最難関であり、ハイレベルな学力が求められます。
医学部をやめて、他大学の他の学部に進むという場合は、編入試験を受験することが可能です。
国公立大学への転学を目指す場合は、受験勉強が必要になるため、その準備に生活の大半の時間を充てることになりますが、合格する保障がないため、別の大学への医学部編入を目指すのはあまり現実的とはいえないでしょう。
学費の安い私立大学への転学
現在在学中の大学よりも、学費の安い私立大学を探して転学する方法もあります。
こちらも国公立大学への転学と同様に、理系学部へ転入し医学部編入試験の受験資格を満たし、医学部編入試験を受験するか、一般受験をすることになります。
もしくは、医学部ではない薬学部や歯学部などの他学部へ編入する道もあります。
私立大学入試に関しても、他大学の医学部に新たに入り直すのが厳しい戦いになることは間違いないでしょう。
また、受験費用や予備校などの受験準備費用もかかってくるため、他大学への受験を検討する場合は金銭面に関しても注意が必要です。
7. クラウドファンディングの活用
7つ目は、クラウドファンディングの活用です。
クラウドファンディングを利用して、学費を募るという選択肢もあります。
クラウドファンディングでは、奨学金やアルバイト、家庭からの援助では全ての学費が払えない状況であることを説明し、目標費用の具体的な使用内訳と、自分が医学部に通う事で将来的に社会の利益になることを明確に伝えることが重要です。
思いが伝わって、誰かが支援をしてくれる可能性があります。
クラウドファンディングサイトでプロジェクトを設立することができますので、もし興味がある方は実際に学費を募っている方を調べて参考にしてみるとよいでしょう。
まとめ
このコラムでは、私立大学医学部の学費が払えないときの7つの対策について解説しました。
私立大学医学部は学費が高額ですが、これらを支払えないと学業の継続が難しくなってしまいます。
奨学金や教育ローンなど、経済的に困窮している医学部生が利用できる制度がありますので、一度自分が対象になっているものがあるか調べてみるとよいでしょう。
情報収集をしてさまざまな選択肢を知ることが重要です。