偏差値が低い医学部を国公立と私立に分けて紹介!志望校を選ぶ際の注意点も解説
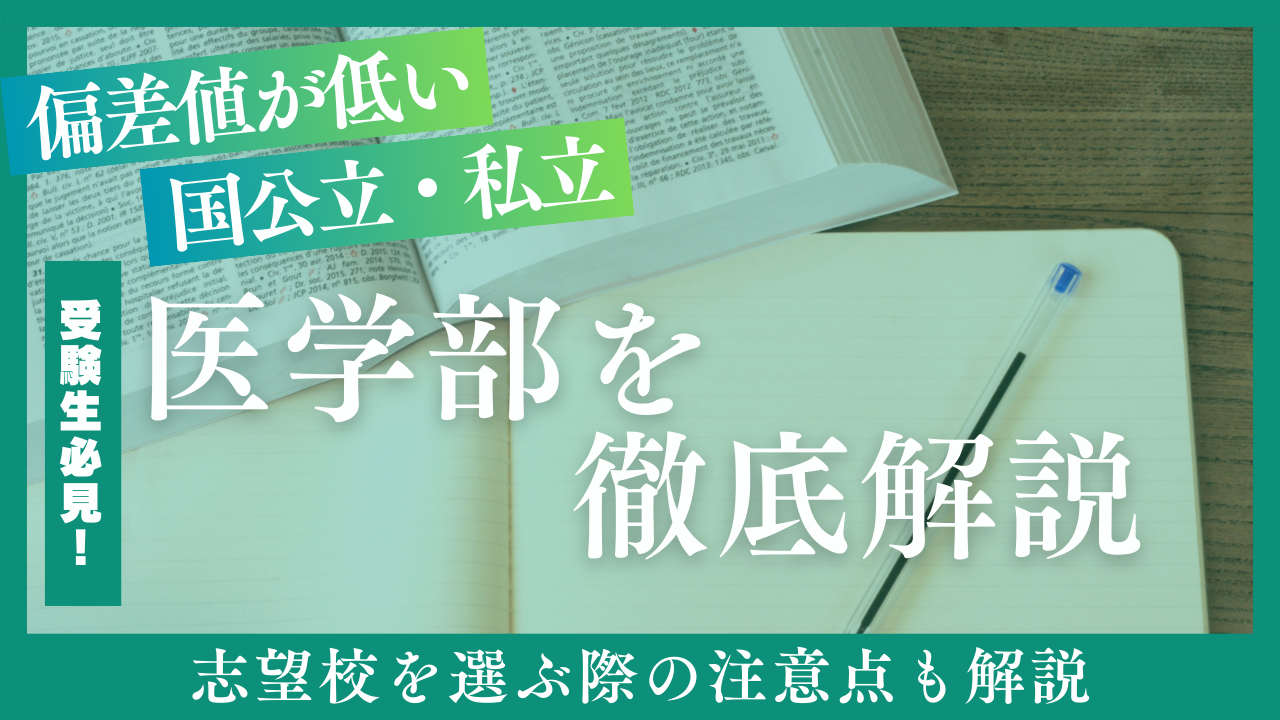
この記事では医学部志望の受験生の方向けに、医学部の偏差値が比較的低い大学についてまとめました。
国公立大学や私立大学で偏差値が低い大学の具体例だけでなく、偏差値が低い医学部の特徴や注意点なども含めて紹介していますので、医学部進学にご興味のある方はぜひ参考にしてください。
偏差値が低い医学部大学の特徴
まずは医学部の偏差値が低い大学の特徴についてまとめました。
都市部からのアクセスがしづらい
医学部の偏差値が低い大学の多くは都市部からのアクセスがしづらいです。
偏差値が低い大学は、地方大学が多くなっています。都市部から遠いため、別の地域から受験者が集まりにくく、倍率が上がらないので、偏差値が低くなっていると見られます。
キャンパスが都市部でないため、遊ぶところがないなど、環境面で後悔してしまう場合もあります。
また、その地域に特化した医療の学習など、地域に密着した医師の育成に力を入れている大学が多く、将来のキャリアプランと合わない可能性があります。
キャンパスの立地や周辺環境などをしっかりと確認しましょう。
推薦枠や地域枠の設定が多い
推薦枠や地域枠の設定が多い大学も偏差値が低い傾向があります。
特に地域枠は、大学によって定員割れを起こしている場合があります。
地域枠では、卒業後の就職場所に条件がつけられており、大学側が指定する医療機関や地域で一定期間就労することが義務付けられます。
卒業後の進路に直接関わってくるので、地域枠や推薦枠での受験が自分に合っているかよく考える必要があるでしょう。
進級が難しい
医学部の偏差値が低い理由として入学後の進級が難しい場合があります。
偏差値が低い大学は、医師国家試験の合格率が低く、留年率が高い可能性があります。
また、進級試験が他大学と比較して難しいことが原因で、留年率が高い場合があるので注意が必要です。
進級が難しい大学は人気が低く、受験生が集まりにくい傾向にあります。
医学部は入学後も膨大な学習量が求められます。留年してしまうとさらに学費がかかってしまうため、大学選びの際は入試偏差値だけでなく進級率や国家試験合格率も加味して考えるとよいでしょう。
後期試験を開催する大学が多い地域
医学部医学科の後期試験は実施大学が少なく、前期試験よりも難易度と倍率が上がる傾向にあります。
そのなかで後期試験の倍率が低い大学の特徴として、その地域全体が後期試験を開催する大学が多いということがあります。
特に中部・北陸地方は、医学部医学科の後期試験を実施している大学が他の地域よりも多いため、受験生が分散し、倍率が比較的落ち着いています。
一方で、富山大学は2022年度から後期試験を廃止したため、今後中部・北陸地方の後期試験の競争率は上がっていくとみられます。
後期試験は全国的に廃止の傾向にあり、さらに倍率と偏差値が上がると予想されるため、注意が必要です。
医学部の創設が間もなくネームバリューがない
医学部の偏差値が低い理由として、創立から年数が経っておらず、ネームバリューがない可能性があります。
新設校ではまだ歴史が浅く、名門大学の医学部と比較すると教育や研究の実績が少なく、受験生が志望校に選ばないことで倍率が下がり、その結果として学力の高い生徒が集まらず、偏差値が低くなってしまっています。
しかし、現在はネームバリューがあまりなかったとしても、今後ネームバリューが上がり偏差値も上がる可能性もあるため、受験校として考えておくのもよいでしょう。
学費が他大学よりも高額
偏差値が低い理由として、学費が他の私立大学と比べて高い可能性があります。
現在医学部のなかで最も入学するのが簡単とされている川崎医科大学は、医学部のなかで最も学費が高く、卒業するまでに4000万円以上かかります。
学費が高いことで入学できる人が限られてしまうため、倍率が低くなると考えられます。
学費だけでも高額ですが、一人暮らしをするとなるとさらに6年間の生活費も必要となり、かなりの費用がかかります。
そのため受験生は、偏差値だけでなく学費についても事前にしっかりと調べておきましょう。
医師国家資格の合格率が低い
偏差値が低い理由として、医師国家試験の合格率が低い可能性があります。
6年間の厳しいテストや実習に耐えたとしても、医師国家試験に合格しなければ医師として働くことはできません。
医師国家試験への合格率は志望校を選ぶ上で非常に大切となっており、合格率が低い大学は教育体制やカリキュラムが十分に整っていないとみなされ、入学を志願する受験生の数も減っていきます。
そうなると倍率も下がり、入試難易度も易しくなります。医師国家試験の合格率はどの大学も毎年公表しているので、受験校を選ぶ指標の1つにしましょう。
偏差値が低い国公立大学医学部
次に偏差値が低い国公立大学医学部をご紹介いたします。
秋田大学
まず、秋田大学についてご紹介します。
秋田大学医学部の偏差値は62.5となっています。また、医学部の学生数は780人程度です。
秋田大学医学部の特徴は、秋田県をはじめとする東北地方の医師不足解消に貢献することを目的としていることです。
地域の医療機関との連携を密にし、学生は早い段階から臨床実習に参加することで、地域医療の現状を肌で感じることができます。
地域医療に興味のある受験生にとっては魅力的な選択肢と言えるでしょう。
また、少人数制で学生一人ひとりに目が行く教育を行っており、きめ細かな指導を受けることができます。
秋田県は自然が豊かで、美しい四季を感じながら学ぶことができるので、ストレスの少ない環境で医学の勉強をしたいという方にもおすすめです。
琉球大学
次に、琉球大学についてご紹介します。
琉球大学医学部の偏差値は62.5となっています。
また、医学部の学生数は約730人です。沖縄県は医師不足が深刻な地域の一つです。
琉球大学医学部では卒業後、沖縄県内の医療機関で勤務し、地域医療に貢献することが期待されています。
また、沖縄は亜熱帯気候であり、本土とは異なる気候病や感染症が問題となることがあります。
そのため、デング熱やマラリアなど熱帯地域特有の疾患に対する研究や、ハブ毒やフグ毒などの海洋生物毒に関する研究も行っています。
沖縄は独自の文化や歴史を持つ地域です。
多様な文化に触れることで、広い視野を持った医師を育成することを目指しています。
高知大学
続いて、高知大学についてご紹介します。
高知大学医学部の偏差値は62.5となっています。
しかし、近年では志願者が増加しており、競争率も上昇傾向にあります。
医学部学生数は700人程度です。高知大学医学部では、高知県の医療機関と密接な連携を図り、地域医療の問題解決に取り組んでいます。
地域住民の健康を守り、包括的な医療を提供できる「家族医」を育成するための独自の教育プログラムを実施しています。
早期から地域医療機関での臨床実習を重視し、地域医療の現場を肌で感じながら学ぶことができます。
また、少人数制教育のため、きめ細かな指導を受けられるのも特徴です。
山形大学
次に、山形大学についてご紹介します。山形大学医学部の偏差値は62.5です。
また、学生数は700人程度です。山形大学医学部では、最先端の医学研究が行われており、学生は最新の医療知識を学ぶことができます。
また、研究活動と教育活動を密接に連携させることで、学生は実践的な医療人を目指すことができます。
他にも、海外の大学との交流や、国際的な学会への参加など、国際的な視野を持った医師を育成するための取り組みが積極的に行われています。
多様な文化背景を持つ人々とともに学び、国際的な医療現場で活躍できる人材を目指しているのが特徴です。
愛媛大学
最後に愛媛大学についてご紹介します。
愛媛大学の医学部の偏差値は65.0となっております。
医学部の学生数は約950人です。愛媛大学医学部も地域医療に根ざした特徴的な教育を行っています。
1年生の早い段階から医療現場を体験し、患者中心の医療である「患者参加型医療」を実践するため早期から患者と接することができます。
また、少人数制教育や充実した教育設備など、学生の成長をサポートする環境も整っています。
偏差値が低い私立大学医学部ランキング
次に、偏差値が低い私立大学医学部ランキングを紹介します。
川崎医科大学
偏差値が低い私立大学医学部の1位は川崎医科大学です。
偏差値は60.0となっています。偏差値が低い理由として、私立医学部の中でも学費が最も高額であることが挙げられます。
6年間でかかる費用は4,550万円〜5,000万円といわれています。
ですが、問題解決型の学習法で学生が主体的に学ぶことを促すなどの独自の教育システム、最新の研究設備などが整っているので、高額な学費を払ってでも医学を学びたいという意欲の高い学生が集まっています。
岩手医科大学
偏差値が低い私立大学医学部の2位は岩手医科大学です。
偏差値は60.0-62.5となっております。
首都圏からのアクセスが不便であることや、学生数や教員数が他の大学と比較して少ないため、多様な教育プログラムや研究環境が整っていないと感じられてしまうことが偏差値が低い理由です。
岩手医科大学は医学部だけでなく、他の医療系学部も併設しており、医学部と他の学部間の連携が活発です。
そのため、学際的な教育を受ける機会が豊富で多角な視点から医療を学ぶことができます。
また、1年次は全寮制です。
個室がありますが、食事・入浴・洗濯などは共用のため、学生同士のコミュニケーションが取りやすく勉強の不明点も解決しやすい等のメリットはありますが、他人との共同生活が苦手な方は大変だと感じるかもしれません。
獨協医科大学
偏差値が低い私立大学医学部の3位は獨協医科大学です。
偏差値は62.5です。獨協医科大学の偏差値が低い理由としては、国家試験合格率が低い点が挙げられます。
2024年の合格率は95%でしたが、合格率が9割を切っていた年もあったようです。
獨協医科大学も医学部だけでなく、歯学部、薬学部、看護学部がある総合大学であるので、幅広い医療分野を学ぶことができます。
また、実物と同様の医療機器を用いたシミュレーショントレーニングを行えるなど研究施設が整っているだけでなく、キャンパス内に公園や運動施設が整備されているので快適な環境で学ぶことができるでしょう。
埼玉医科大学
偏差値が低い私立医学部の同率3位は埼玉医科大学です。
偏差値は62.5です。埼玉医科大学は埼玉県の中で唯一の医学部となっています。
アクセスは都心部にもアクセスできるため良いのですが、東京都内にある他の医学部と比較される場合が多いです。
また、埼玉医科大学は1972年に設立された新設医学部となっています。
学費は、6年間で約3,900万円となっており、高額で医学部を志望している優秀な生徒は他の学費の安い大学へ流れ、偏差値が低くなっていると考えられます。
しかし、埼玉医科大学は施設や医療設備が非常に整っていること、少人数制の授業が多く採用されています。
北里大学
偏差値が低い私立医学部の同率3位は北里大学です。
偏差値は62.5です。北里大学は神奈川県にあり、アクセスが良いものの埼玉医科大学と同じく東京都内の他の医学部と比較されることが多いです。
学費は約3,800万円と高額であるため人が流れ、偏差値が低くなっている可能性があります。
また、医学部の不正入試が2018年に起こり、その影響から偏差値が低くなった可能性もあります。
北里大学は医療系の総合大学であるため、他の学部と関わりを持つことができます。
偏差値が低い医学部を選ぶ際の注意点
偏差値が低い医学部を選ぶ際の注意点についてご紹介します。
入学後の学習環境を確認する
まず、入学後の学習環境についても確認しておきましょう。
一つの学習環境としてアクセスが挙げられます。
偏差値が低い医学部ではキャンパスが田舎にある場合が多く、交通アクセスが不便で怠けてしまう可能性があります。
また、周りに遊べる場所もないため憧れていた大学生ライフがあるならば、描いていた未来ではない可能性があります。
そのため、自分の実家、または一人暮らしが可能か、どのように大学に通うのかをイメージしておきましょう。
医師国家試験の合格率をチェックする
次に医師国家試験の合格率をチェックしておきましょう。
医師として働くためには、医師国家試験に合格しなくてはなりません。
偏差値が低く医師国家試験の合格率が低い大学だと、入学してからの勉強が理解できず、留年や国家試験に合格できない場合があります。
そして、試験に合格できなかった場合は国試浪人となりますが、その場合も費用がかかるため注意しておきましょう。
医学部に合格できたなら医師国家試験も合格できるよう、勉強を継続するようにしておくと良いです。
地域枠の条件を十分に理解する
次に地域枠での条件を十分に理解しておきましょう。
地域枠だけでなく、一般枠であっても医師不足に悩まされている都道府県ではその地域で働くよう指導されることがあります。
地域枠であれば、大学側が指定している地域や医療機関での勤務が義務となっていることを理解した上で受験をすることになります。
大学ごとに条件が異なる場合があるため、自分の志望校はしっかりと調べておきましょう。
将来のキャリアプランを考慮する
次に将来のキャリアプランを考えておきましょう。
偏差値が低く受かりやすいからという理由だけで受験し合格してしまうと失敗する可能性があります。
そのため、その大学を受けるにあたって合格したらどのようなキャリアプランを描くのかは受験前に考えておきましょう。
そして、合格してからも後悔のないように学び、理想のキャリアを描いていきましょう。
まとめ
今回は医学部の偏差値が比較的低い大学やその特徴について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
医学部は偏差値が低いといっても最難関学部で他の学部と比較すると非常に難しいです。
もし、受験する場合は継続的な努力が必要となるため、早い時期から勉強することがおすすめです。