「医学部編入はやめとけ!」といわれる理由! 編入へのポイントも解説
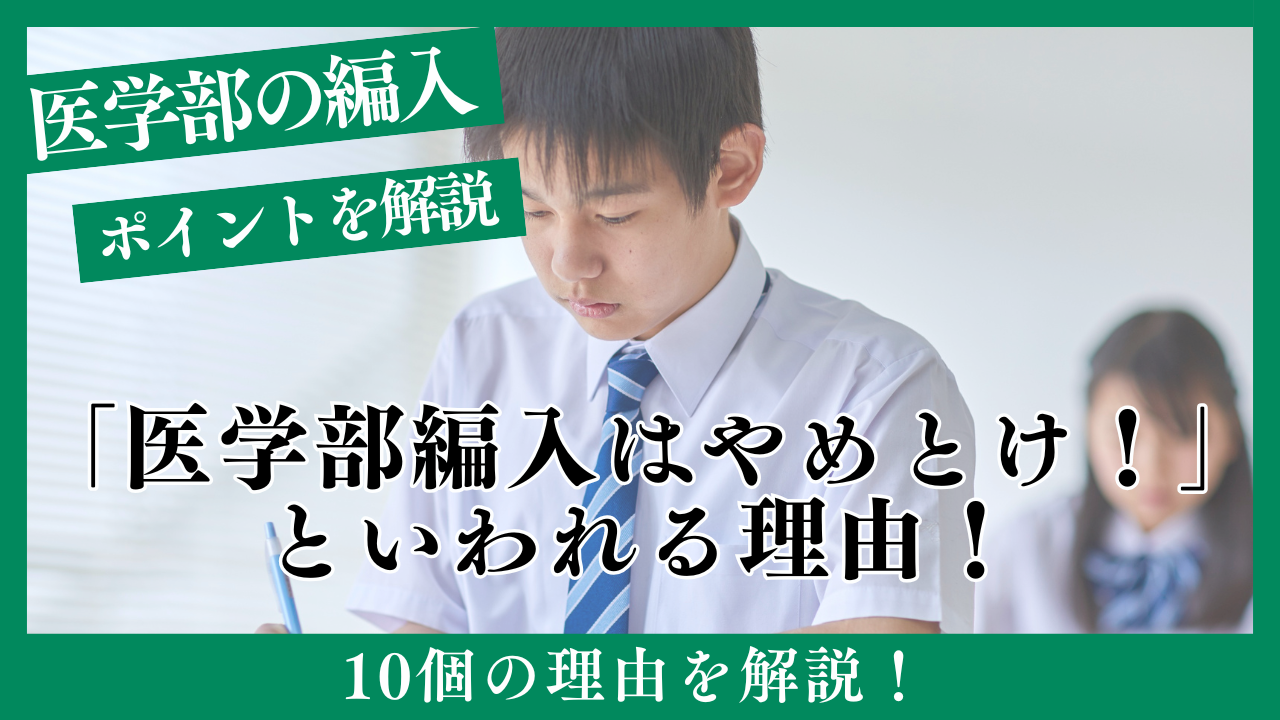
この記事では、医学部編入を「やめとけ」といわれる10の理由をまとめました。金銭面やストレスといった医学部編入の際に注意しておきたいポイントや、それらを踏まえて>医学部編入を成功させるための3つのポイント</markについて解説していますので、医学部編入にご興味のある方はぜひ参考にしてください。
なぜ医学部編入は「やめとけ」といわれるのか
なぜ医学部編入は「やめとけ」といわれるのでしょうか。ここでは10の理由について説明します。
1. 想像以上の時間と労力が必要
一つ目は、想像以上の時間と労力が必要な点です。
睡眠時間の激減
医学部の編入試験は難関で出題範囲が広いため、合格には膨大な勉強量が求められます。そのため、想像以上の時間と労力を勉強に費やす必要があります。朝は早く起きて、夜は遅くまで勉強するといった徹底的な時間管理が必要で、睡眠時間が激減してしまう場合があります。医学部編入に成功した編入生は、大学の通常授業やアルバイト、友達との遊びの時間を犠牲にして勉強時間に充て、お風呂や通学中などの隙間時間も活用し、勉強漬けの日々を送っていたようです。受験に自分の時間と労力を、どれだけ投資できるのか十分に考えてから受験を決断することが重要でしょう。
社会生活との両立の難しさ
社会人の方は、現在勤めている仕事との両立は難しいと考えていいでしょう。学生の方も、同じく通常の学業と編入試験の勉強を同時に進めるのは非常に困難です。集中力が落ちて、どちらも中途半端になってしまう可能性があります。社会人の再受験生や編入生は仕事を退職、もしくは両立しやすい仕事に移行する人が多いです。環境が許す場合は、編入試験への準備に集中するために仕事を減らしたり、退職する方が、仕事を今まで通り続けながらするよりも遥かに勉強時間を確保できます。仕事や学業と両立するとなると、精神面と肉体面の疲労は大きくなります。無理なく自分に合った受験生活を送ることができるか考えてみる必要があるでしょう。
2. 経済的負担の重さ
二つ目は、経済的負担の重さです。
予備校費用の高騰
医学部受験に対応している予備校は、普通の予備校と比較して授業料が高いことが多いです。特に医学部編入試験の情報は少ないため、医学部編入実績のある予備校に通うことは情報収集という意味でも有益ですが、近年予備校費用が高騰しているなかで、さらに医学部編入に特化した授業となると、かなりの金銭的負担が考えられます。予備校を利用せず、独学で合格している方も中にはいらっしゃいますが、少しでも情報を得て、かつ予備校費用を減らしたいという方は、自分に必要な授業を単科で受講することも一つの手といえます。また、お金や時間に余裕がある方は編入試験用のコース授業を利用し、それらをメインにして受験勉強を行うのも戦略としてあるでしょう。
生活費と学費の二重苦
生活費と学費を自分で働きながらまかなう必要がある場合は、入学後は金銭面、体力面、精神面、また時間的な面においてもとても厳しい学生生活となります。大学近くで一人暮らしを行う際は、家賃や光熱費、食費もかかります。また、社会人でお子さんや配偶者など家族がいる方は、さらに生活費がかかる場合があります。医学部生は日々の授業と学習だけでなく夜間実習なども多いため、自由に使える時間があまり多くなく、また不規則になりがちです。都市部では家庭教師など医学部生の単価の高いアルバイトがありますが、そのような求人が少なかったり、編入生では大学受験の範囲を忘れてしまっていたりして、条件がいいアルバイトを見つけることが難しいかもしれません。生活費と学費は医学部生を続ける上で必要ですので、自分の環境でどの程度まかなえるのか金銭的な見通しを把握しておきましょう。
3. 精神的ストレスの限界
三つ目は、精神的ストレスの限界です。
競争の激しさによる焦り
編入試験は競争率が高く、焦りや不安を感じることが多いです。医学部を目指す受験生は全国にいるため、強いプレッシャーに押しつぶされてしまいそうになる人もいるでしょう。受験は人生における大きなイベントで、今後のキャリアプランなども考えると、より精神的な負担が大きくなります。また、勉強しても模試で思ったような成績が取れなかったり、周りと比べてしまって自信をなくしてしまうことがあります。ストレスが蓄積すると、集中力が低下して勉強に支障が出てしまう場合もあるため、ストレスとうまく付き合っていくことが重要です。
孤独感との闘い
編入生は周りに同じ目標を持つ仲間が少なく、孤独感との闘いになることがあります。また、受験勉強中は、基本的に一人で長時間勉強に励むことになるので、家族や友人と過ごす時間が減って、より孤独感を感じやすいでしょう。編入学を目指す方の中には、直前まで大学や会社の人たちには話さない方も多くいます。医学部受験はストレスが多いですが、精神面で健康を損なわないように、仲間を見つけたり時にはリフレッシュを行ったりすることが重要でしょう。
4. 年齢によるハンデキャップ
四つ目は、年齢によるハンデキャップです。
若い学生との体力差
編入生は一度大学に入学している方々のため、大学受験の現役生よりも年齢が上になります。また、社会人で受験される方は30代以上の方も多く、10代や20代の方よりも体力面で不利と感じることが多いかもしれません。受験勉強には時間や精神の余裕だけでなく、長時間勉強をし続ける体力も必要となります。また、医学部生の学生生活はとてもハードなため、入学後はより一層の体力が求められます。
5. 編入後の学習の厳しさ
五つ目は、編入後の学習の厳しさです。
基礎医学の膨大な量
医学部編入生は、編入年次以前の授業を受けることができないため、自力で基礎医学の膨大な範囲をインプットする必要があります。編入生のバックグラウンドにもよりますが、薬学部出身の方は学習内容が重なっている部分もあり、進級のハードルが比較的低く有利と言われています。入学後の通常授業で必要となる学習は膨大ですが、編入年次以前の内容の理解がないままだとついていけないため、医学部編入の際は膨大な量の学習が必要となります。
臨床実習での苦労
臨床実習では、指導してくれる後期研修医が自分よりも年下であるなどの苦労があります。また、拘束時間が長いため、想像以上に体力勝負であると感じるケースもあるようです。臨床実習では、座学で学んだ学習を実際に現場ではどのように対応しているのかを学びます。教科書通りではなく、臨機応変な対応となるので、臨床実習は肉体的にも精神的にも非常に大変です。
6. キャリアの中断リスク
六つ目は、キャリアの中断リスクです。
元の職場への復帰の難しさ
医学部編入を目指すにあたって、仕事を辞めて勉強に専念する方は多いと思います。その際にネックとなるのが元の職場への復帰の難しさです。仕事と両立して医学部を受験される方もいらっしゃいますが、その場合でも医学部編入後は、仕事を行いながら学生生活を送るのは困難でしょう。医学部編入後は新たなキャリアを歩むことになるので、今までのキャリアを中断するというリスクは生じるでしょう。
新たなキャリアパスの不確実性
新たなキャリアパスが不確実であることもリスクです。受験準備のために退職しても、編入試験に合格しなかった場合はキャリアをまた考え直すことになります。また、医学部に編入できても、仕事内容が自分に合っていなかったり、労働環境が想像以上に過酷だと感じてしまったりして、途中で辞めてしまう可能性もあります。医師のキャリアは卒業後に始まるため、学生期間中にまた人生の方向転換を行うとなると、また数年キャリアの断絶が生まれてしまいます。編入を目指す際には、新たなキャリアパスの不確実性にも注意しておくことが必要です。
7. 家族や周囲の理解を得る難しさ
七つ目は、家族や周囲の理解を得る難しさです。
経済的自立からの後退
編入を目指す際は生活が勉強中心のものとなるので、結果として経済的自立から後退することが考えられます。今まで家庭内の収入を支えていた方が受験生となる場合、経済面のフォローをどのようにするのかしっかりと考える必要があります。また、編入後も学生生活は多忙で不規則なものとなるので、経済的に自立できるほど稼ぎながら医学部に通うのは厳しいといえます。経済的自立からの後退は免れないため、あらかじめ金銭的な計画を立てておくことが大切です。
周囲の反対意見との葛藤
周囲からあなたのためを思って反対される場合もあります。その場合は自分の中で葛藤が起こるでしょう。家族や友人からはリスクを負って、さらに経済的にも負担がある中で編入するのかと反対されるかもしれません。そのため、もし反対されたとしても成し遂げたいという強い気持ちがあるのかを考えてみましょう。
8. 合格後の現実とのギャップ
八つ目は合格後の現実とのギャップです。憧れの医学部に編入できたとしても、編入や医師についてしっかりと調べておかないとマイナスなギャップにつながるかもしれません。
理想と現実の医療現場の差
医療現場では人を助けることのできる場所というイメージが強いです。もちろんその通りですが、治療の施しようがない場合もあります。意思疎通がうまくできなくなった状態などがあり、そういった医療現場での理想と現実でギャップが生まれないように、医療現場についてしっかりと調べておきましょう。
長時間労働
医師は人の命を預かっているため、長時間労働や夜勤も考えられます。医師の業務は多岐にわたっているところや、診療時間外・休日にも業務を行っているのが今の現状です。実際に1週間に60時間以上働いている医師は41.8%もいます。改革はされてきていますが、残業はあるという認識を持っておきましょう。また、就職する病院や診療科によってプライベートの時間はほとんどない場合もあります。
9. 国家試験のハードルの高さ
九つ目は国家試験のハードルの高さです。医学部に入学しても、医師国家試験に合格しなくては医師にはなれません。そのため、編入できたとしてもそこから勉強し続けることが必要です。ギャップを感じてしまわないように、勉強する習慣はつけておきましょう。
卒業までの長い道のり
一度大学を出ている場合、編入であってもそこから卒業まで長い道のりが必要となります。2年次編入か3年次編入がありますが、編入前の授業は取れないことや単位を取り切って卒業しないといけないため、履修範囲が難しいうえにやらなくてはいけないことが多くあります。そのため、卒業まで長い道のりがあると覚悟しているほうが良いです。
国家試験合格率の厳しさ
国家試験合格率が厳しいこともギャップとなります。医師国家試験では、単純な暗記だけではなく、臨床的な判断力や問題解決能力も求められます。選択肢や問題の表現が非常に難解で、正しい答えを導くためには、深い理解が必要です。国家試験に合格しなければ、国試浪人となって来年度の受験に備える必要があります。国家試験は現役生では毎年90%以上の合格率です。しかし、国試浪人をすればするほど合格率は低くなっていきます。
10. 編入生特有の孤独感
十つ目が編入生特有の孤独感です。
既存のコミュニティへの溶け込みにくさ
編入をする場合、2年次か3年次からが一般的ですが、その時点でコミュニティができており、そこに溶け込むことは非常に難しいです。自分から話しかけられないタイプである場合は困難でしょう。また、相手のコミュニティが快く受け入れてくれるかもカギとなっています。編入生として最初は支援されにくい場合もあり、そんな中でも自分の軸をしっかりと持っておきましょう。
年齢差による価値観の違い
また、年齢差による価値観の違いも生まれてくるかもしれません。高校から現役で入学した場合と編入して入学した場合では年齢がかなり離れています。そこで考え方や価値観が違い、うまくいかない場合もあります。コミュニケーションの取り方や意見が食い違うこともありますが、その際にどう対応するかが大事です。
医学部に編入するためのポイント
続いて医学部に編入するためのポイントについてご紹介します。
1. 徹底的な自己分析と目的の明確化
まずは自己分析を確実に行いましょう。自己分析をすることで今何が弱点で何が強みなのかがわかります。そこから目標を立てましょう。医師になるためには医療に対しても強い目的意識が必要となります。この目的は精神面・体力面でもモチベーションとなります。まずは大きな目的として医学部に編入することを設定し、そこから達成できた際に目に見える小さな目標を設定していきましょう。その際には編入試験の科目や形式、各大学の試験内容を確認し、何をどのように学習するかを明確にします。
2. 効率的な学習戦略の構築
また、受験においては効率的な学習戦略の構築が非常に重要です。医学部編入試験では、基礎的な自然科学の知識(生物学、化学、物理学など)が問われることが多いです。したがって、まずは基礎的な内容をしっかりと理解することが重要です。そして、知識の定着を図るため、問題集を解くことも重要です。解説をきちんと読んで理解し、間違えた問題は繰り返し解くようにしましょう。難易度の高い問題集や参考書を使う前に、基本的な理解を深めるために標準的な教科書で復習しましょう。志望校が決まっているならば、その大学ごとの傾向・対策を行うのが一番効果的です。編入試験の過去問を集め、出題傾向や頻出分野を把握します。特に出題されやすい分野や形式(記述式、選択式、面接等)に注力します。また、自分一人で戦略をたてられない場合は、医学部受験予備校に入学し、戦略アドバイザーと一緒にたてるのも効果的です。
3. メンタルヘルスケアも重視
そして、メンタルヘルスケアも重視しておきましょう。医学部編入では非常に孤独を感じやすいです。まずは、睡眠、食事、運動などの健康管理を怠らないことが、長期的な学習において重要です。また、ストレスや疲労を軽減する方法(趣味の時間や軽い運動など)を取り入れることが、学習の効率化に繋がります。医師という職業は長時間勤務であったり、ストレスも多く感じる可能性があります。医学部に編入し、国家試験に合格し、医師になったとしても、メンタルをいい方向で保てるように、医学部編入を目指す時期から自分にとって効果的なストレス発散法を身につけておきましょう。
まとめ
今回は医学部の編入について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。編入試験は様々な要因からやめておいたほうが良いとよく言われます。しかし、今回ご紹介したやめておいたほうが良いというポイントを理解したうえで受験することでギャップが少なく、編入試験を成功させることができます。ぜひこの記事を参考にして、編入入試にチャレンジしてみてください。